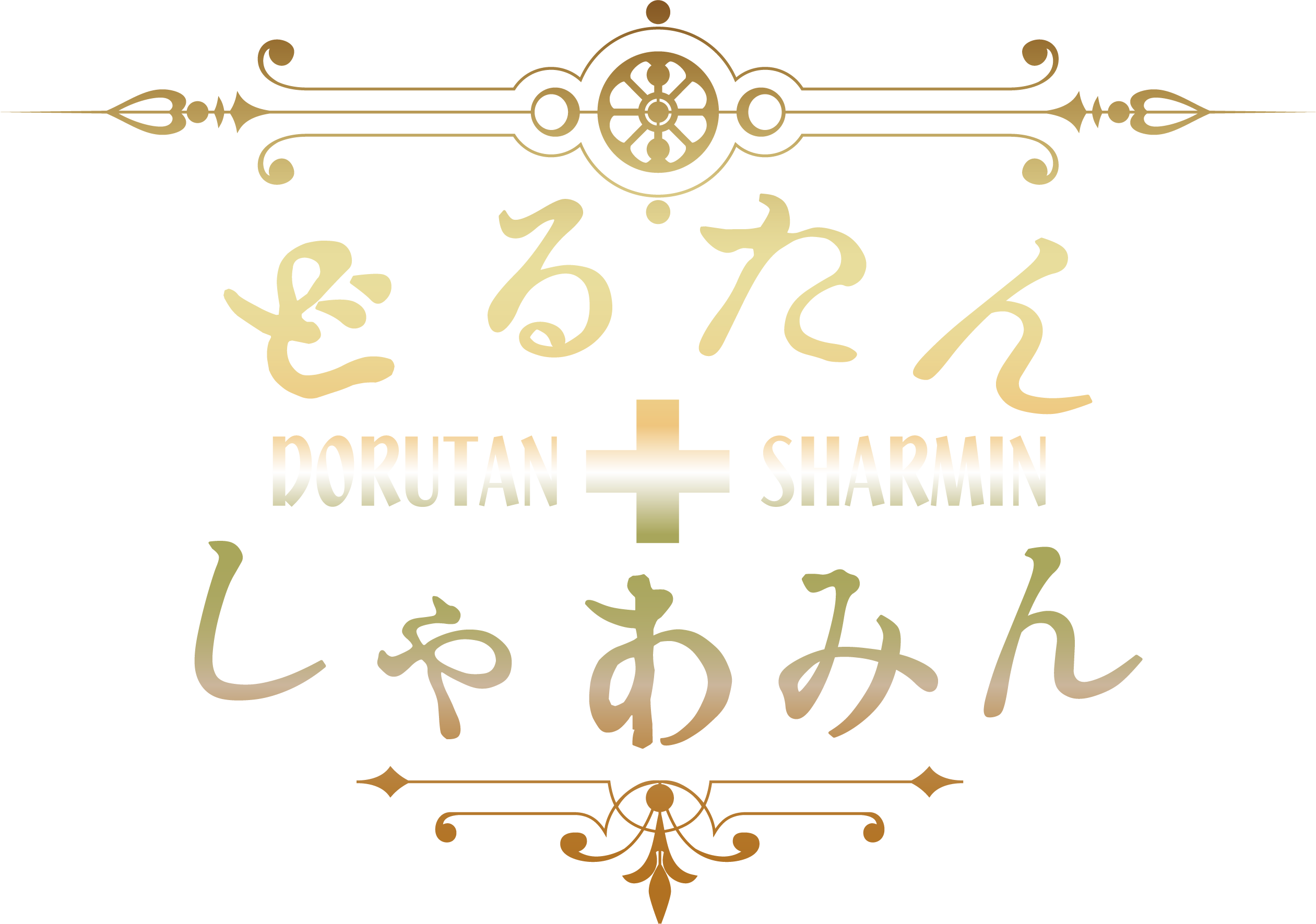『エリック・サティ詩集』藤富保男 訳編
私を形成しているもの
今の自分を形成する一部になっていると言えるほど印象に残る様々なものを「私を形成しているもの」としてとりあげていきます。他のSNSなどに投稿したものを加筆修正して再掲載しているものもあります。
※この下に書かれた年号は作品の発表年ではなく私がその作品に初めて触れた(と思われる)年。またはそのイベント、出来事を経験した年。
※ただの思い出話です。
その他の私を形成しているものたち
私を形成しているもの 年譜(INDEX)
1991
エリック・サティといえば、主にピアノ曲の作曲家として有名だけど、詩集を出している。
(いや正確には詩集を出版したわけではないのだけど、それは後述)

サティの詩(?)から発せられる言葉のイメージがたまらなく好きで、たまにページを繰りたくなる。
どこかシニカルでユーモアがあって、それはサティの音楽と同じ質のもの。
というよりも、これは音楽と一体となった詩。
特に前半に収載された『スポーツと嬉遊曲』は、すべてに手描きの楽譜が添えられている。
もちろんその楽譜は音楽作品としても独立して演奏されている。
例えばこんな具合に

「花火」という短い詩、そして楽譜。
言葉と共に音を聴くと、心の中にイメージが広がりとても面白い。
イメージが広がるというよりも、サティの描いたイメージが伝わると言った方が正しいかも知れない。
「ブランコ」「狩」「ゴルフ」などなど、多種多様なシーンを音と言葉で切り取っている。
単独のピアノ曲を聴く時の楽しみとは、ちょっと違う何か洒落たショートコントでも観るかのような面白みを感じるのだ。
この本の後半は、少し長い単独の詩編が収められているのかな、と初めは思っていたのだけど、あれ、このタイトルは?と調べてみるとほとんど(たぶん全部)曲がある。
なるほど、カヴァーの折り返しに添えられている文をちゃんと読んでいなかった。
「サティは詩人ではない。楽譜の余白にしるされたサティのことばが、よく見ると詩にみえるので、藤富保男さんがそれらを訳し、故人サティにはないしょで「詩集」にしてしまったのである。(読売新聞)
この詩集の成り立ちはそういう事。
冒頭に「音楽と一体になった詩」と書いたけど、それは当たり前。
はじめてこの本に接した時の気持ちで書きました。
この本は、これまでも、これからも、何度もページを繰る。
サティの音楽を繰り返し聴くように。
きっとそんな本。
【どるたん】
作詞、作曲、歌とギター担当