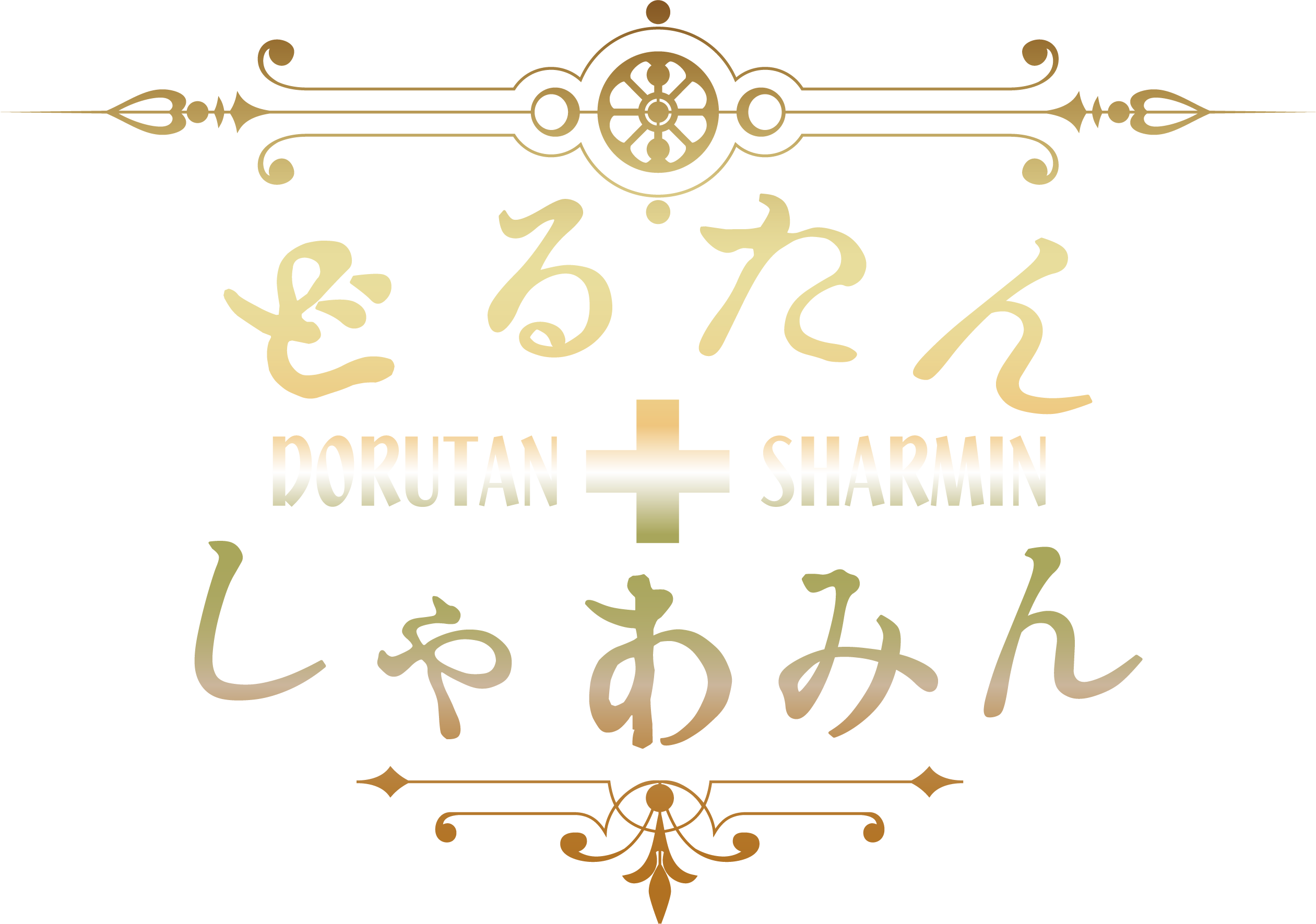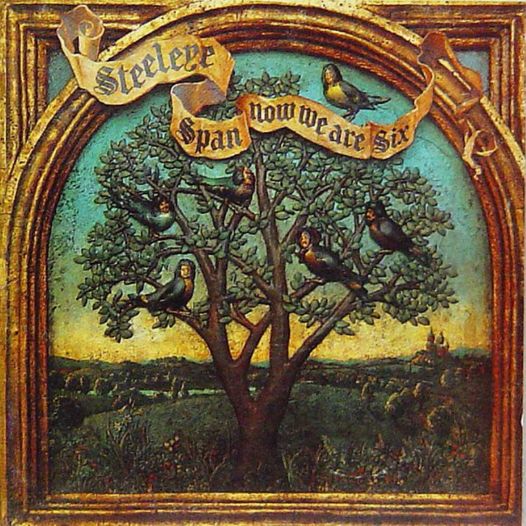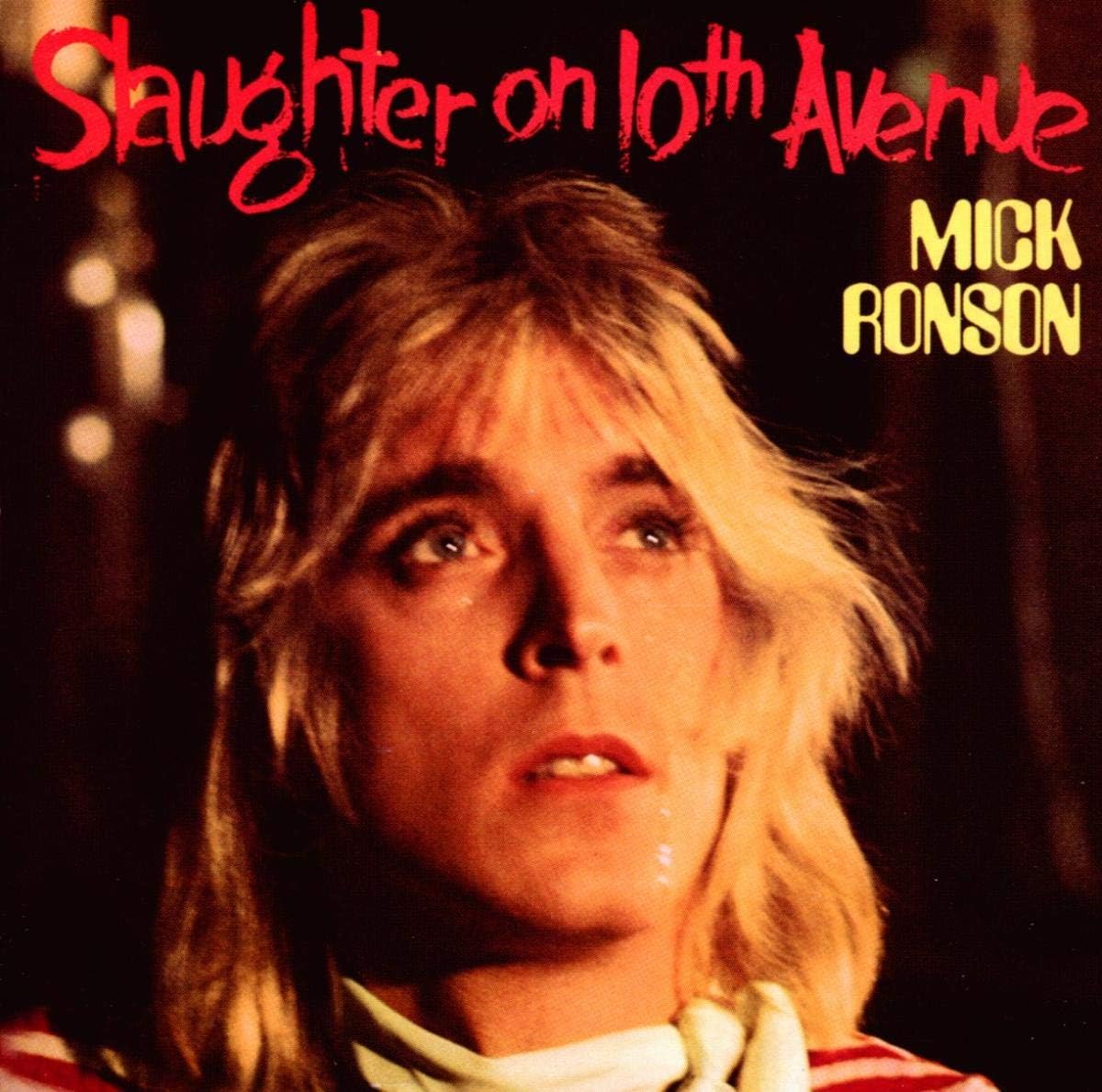私を形成しているもの
今の自分を形成する一部になっていると言えるほど印象に残る様々なものを「私を形成しているもの」としてとりあげていきます。他のSNSなどに投稿したものを加筆修正して再掲載しているものもあります。
1976
小室等『いま生きているということ』(1976年発売)
歌「いま生きているということ」との出会い
1976年のある日、私、高校1年生の時。
その前年のフォーライフ・レコード(吉田拓郎、井上陽水、泉谷しげる、小室等の4人で設立したレコード会社)設立のニュースなどで、いや、その前から、存在は知っていたのだけど、小室さんの音楽をまだあまりしっかりと聴いた事はありませんでした。
そのTV番組で小室さんが歌ったのは「いま生きているということ」
淡々と歌いはじめた、その歌。言葉のひとつひとつが、心に残り、いつの間にか目も耳も心も完全にTVにくぎ付け状態。
アルバム『いま生きているということ』購入
その静かな熱唱に激しく胸を打たれた私は、ほどなく、この歌がタイトルソングとなっているアルバム『いま生きているということ』を購入。
それだけでも、充分な理由なのだけど、もうひとつ購入の意志を決定づけた理由があって、それは、この頃放送されていたTVドラマ「高原へいらっしゃい」の主題歌「お早うの朝」が収録されていたこと。
ただこの「お早うの朝」に関しては、(購入当時)ちょっとがっかりする事もあって、それは後述。
まずは、「いま生きているということ」と「お早うの朝」2曲をお目当てに購入したわけですが、購入時~購入後に知るあれこれもありました。
ただ、当時、15歳、高校1年生の私は、(なんかスゲー!とは思っていたけど)その有難みを今ほどは実感できていなかったと思います。
さて、聴いてみての感想です。
2つの「お早うの朝」
まず、お目当ての1曲「お早うの朝」
VIDEO
それがこのアルバムの「お早うの朝」は、テンポも遅く、歌も朗々とした歌い方、あまりの違いに愕然としました。どういう事!?と。
あの軽快な「お早うの朝」が心に残っていて、それが目当てで買ったという面もあるので、はじめのうちはちょっとがっかりしたわけです。
このアルバムヴァージョンも徐々に好きになりましたが、TV主題歌版シングルヴァージョンの「お早うの朝」がどうしても聴きたくて、後にシングル盤も購入しました。
そのがっかり感とも共通するのですが、このアルバム全体の音が、当時の私にはちょっと大人過ぎたような面があって、はじめのうちは、あまり馴染めなかった気がします。
「いま生きているということ」を聴いて気づいたこと
そんな中、このアルバム購入の一番のお目当て「いま生きているということ」だけは、はじめからダイレクトに心に飛び込んできました。
長い曲の中盤で「いまブランコが揺れていること」以後、何小節か。
歌詞カードを見ても、その部分の歌詞は記載されていない。
若干、疑問はあるものの、ジャケット写真のブランコこそが、その「ぼくが作ったブランコ」なのだろう、と思い至る。さらに裏ジャケットをよく見ると、ブランコ写真についての記載があり、思った通り、小室さんが娘のために作ったブランコだという事が記されていました。
という事は、あの部分は小室さんが付け加えたというか、アドリブ的に歌ってしまった歌詞なのだろう、と考えてほぼ間違いないでしょう。
この件については、その後数十年経った2017年5月に直接小室さんに確かめたところ、思った通りの答えが返ってきました。
その際、「『いま生きているということ』のアルバムに入っている「お早うの朝」が思ってたヴァージョンと違ったので、シングル盤も買いました。」という話をしたら、笑いながら「それはごめんなさい」と謝られてしまいました。いやいや、そんな~LPとシングル両方買って良かったと思っています。
2017年5月 和久井光司さん主催ボブ・ディラン・サミット2017にて(どるたん/小室さん/PANTAさん)
「いま生きているということ」と私の生き方
で、この「いま生きているということ」が、なぜこれほどまでに心に響いたのか、という事について触れたいのですが、それは「いま」「生きている」ということ自体が、子供の頃(具体的に言うと小学2年生時のある日)から、自分自身のテーマになっていたから。
歌詞の中の
生きているということ それはミニスカート それはヨハン・シュトラウス
ここで、いつも泣きそうになります。
そして、この後つづく
そして
に深く納得し、これからも、そうやって生きていこうと思うのです。
変わっていったアルバム全体の印象
はじめの方で書いたように、このアルバム全体の音に馴染むのに少し時間がかかったのですが、聴き込んでいくうちにかなり印象が変わっていきました。
はじめのうちは、なんという事のない情景を描いただけの詞だと思っていたものが、心の中で膨らんでいきました。
例えば「高原」という歌
野苺の花の上の露のひとしずく
この3行だけでも、美しいイメージ、情景が心に浮かぶのだけど、さらに
朝は峠をこえてやってきた
と続き、なんだかたまらない気持ちになります。
そして、ムーンライダーズのカントリー調の演奏がどこか大人びて聴こえて、15歳の私にはすぐには馴染めなかったのですが、とても心地の良い、心に沁みる音に変わっていきました。
また、年を経ると、15歳の頃、あまり有難みが分からなかった、谷川俊太郎、ムーンライダーズ、矢野顕子の存在も自分の中でどんどん大きくなっていき、それに伴い、さらにこのアルバムの存在も大きくなっていくのでした。
このアルバムを買ってから、約50年。ほぼ半世紀!?
その間、毎年必ず針を落とす特別なレコードであり続けています。
きっとこれからも。