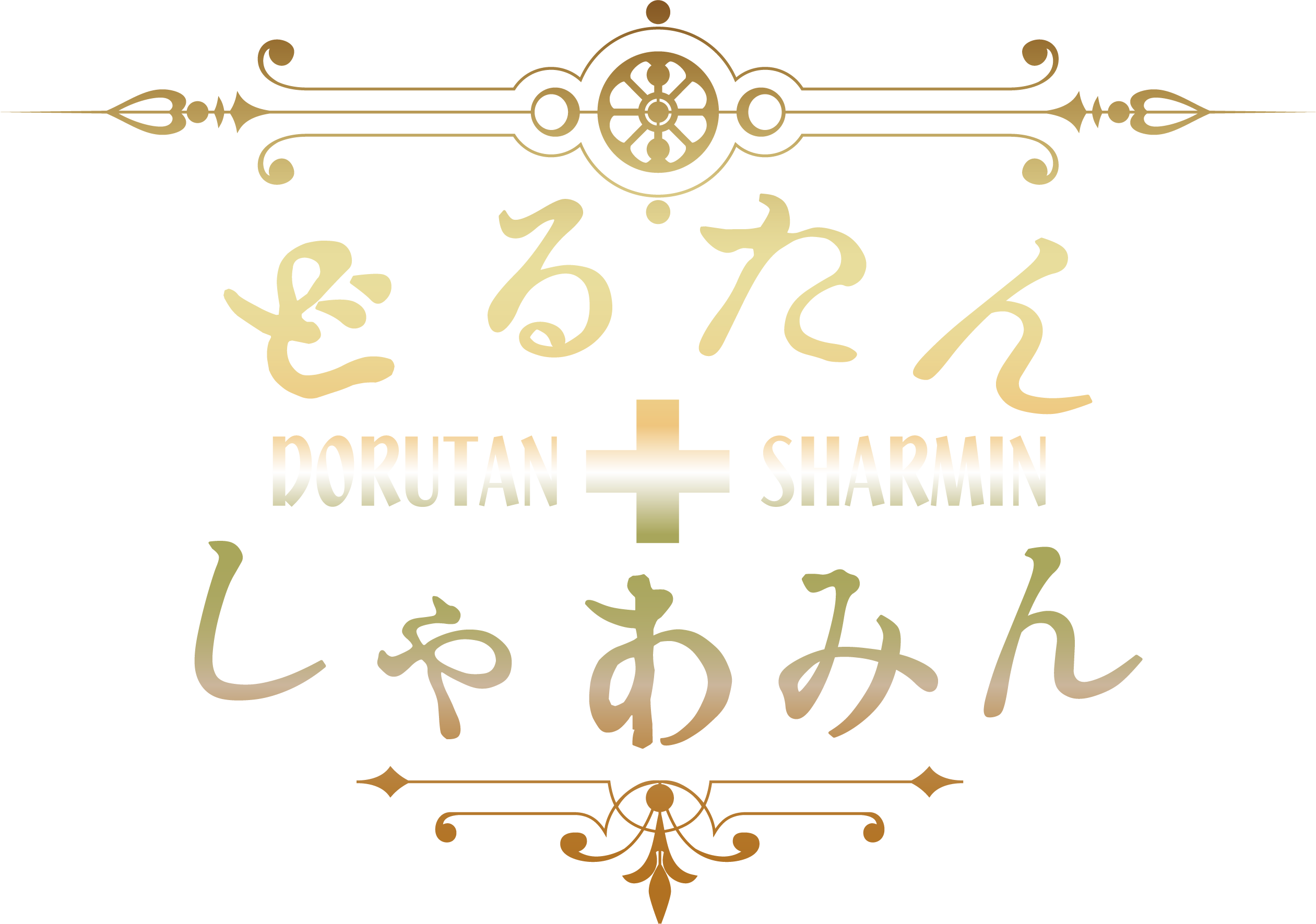埼玉ピースミュージアムに行ってあれこれ考えた
2024年6月11日 埼玉 東松山市 埼玉ピースミュージアム(埼玉県平和資料館)

6月11日に埼玉ピースミュージアムへ行ってきた。
そこで考えた事などいくつか書いておこうと思う。
1.語りつぐ
エントランス付近の壁にあったレリーフ的な文字
平和をかたりつごう、永遠に・・・・・・

揚げ足をとるわけではないのだけれど、このミュージアムに展示してあるものは、ほとんど全て戦争に関するもの、戦時中の生活に関するもの、ここで語りついでいるものは、平和ではなく、戦争。
しかし、戦争を語りつぐことで見えてくるのが、平和のありがたみ、平和であることの大切さ。
直接的に平和を語っているわけではなくても「平和をかたりつごう、永遠に・・・・・・」という言葉に、深い意味と意義を感じる。
語りつぐ者の存在
私が子供の頃には、戦争(第2次世界大戦)は、わりと身近なものだった。
私の親は、子供時代に戦争を経験している世代。
祖父は、硫黄島で戦死している。
今放送している朝ドラ『虎に翼』に出てくるハーモニカを吹く傷痍軍人も、私が子供の頃には実際に目にしていた。
また、マンガや子供向けの本などにも、戦争はよく描かれていた。
私が子供の頃に、強く戦争と平和を意識したのは、ちばてつやのマンガ『紫電改のタカ』が最初だったと思う。
その後も、実際に戦地に行った水木しげるの戦記マンガや、こども時代に戦争を経験した手塚治虫やちばてつやの数々の作品、マンガ雑誌に連載されていた『はだしのゲン』などなど、戦争の悲惨、理不尽に触れ、平和を思う心を育まれてきた。
児童書の『ビルマの竪琴』や『つしま丸のそうなん』なども読んだ。
映画やテレビ番組の数々も。
子供の頃に「戦争を知らない子供たち」という歌がヒットしたのだが、書物などを通しての知識としても、実際に目にしたものや家族や教師の話を通しての実感的な意味でも、かろうじて戦争を知っていたのだ。
自分自身の体験としては知らなくても、戦争はまだまだ身近な事象としてあったし、戦争と平和について知り考える時間はとても多かったと思う。
私のように積極的に知ろうとする者と、無関心な者とでは、考える時間にも内容にも大きく隔たりがあるのだろうけれども、世代として戦争は身近なものだったと言えるだろう。
語りつぐ者の不在とピースミュージアムの意義
転じて現在の子供たちが、どれだけ戦争について知り、平和を考える機会があるのだろうか?
子ども時代に戦争を経験している私たちの親世代は、既に亡くなっている方も多く、実際に戦争を経験していない私たち世代は、自分事としての戦争は語れない。
私自身の事を振り返っても、子供たちに戦争の事を語ったり、話し合ったりした事はないかも知れない。
色々な書物や映画などで戦争に触れ、戦争と平和について深く考えてきた私のような人間でも、子供世代に語りつぐという事をしていないのだ。語りつぐ体験はなくてもせめて「どう感じる?どう考える?」という問いかけぐらいは出来たのではないだろうか。
そして社会全体の風潮(というか政権の考え方)として、戦争当事国としての歴史を、あまり悲惨なものとして語りつがせないようにしているような空気さえ感じる。
かつては毎年のようにテレビ放映されていた映画『火垂るの墓』も最近では放送されることもない。
『はだしのゲン』を図書館に置くなという勢力もある。
そんな中、このようなミュージアムの存在は有意義だと感じる。
語りつぐものはいなくなっても、物が資料が物語が語りついでくれるから。

税金の使い道
ところで、この埼玉ピースミュージアム、実に立派な建築物なのだ。
展示スペース、展望塔、映画上映設備などなど。
これ、一体誰がお金を出して作ったのだろうか?
埼玉県?
だとしたら私たちの収めた税金が使われているわけです。
こういう事は県議会をしっかりとウォッチしていれば分かる事だろうし、新聞や広報にも載っていたのでしょう。でも、私は、知らなかった。知らないうちに出来ていました。
文句が言いたいわけではありません。
むしろ上に書いたように「有意義だと感じている」ので、有意義なお金の使い方をしてくれたと、有難くさえ思っています。
東京都のように下品な(と私は感じています)プロジェクションマッピングに事業費48億円つぎ込んだわけではないので。
この48億円という金額だって本当にいかれた金額で、どう考えても48億円もかかるものではないでしょ?どこに流れてるのそのお金。
そんな税金の使い方をされてしまうと、残念という感情では済まない気がする。
(この件に関してだけかも知れないけど)埼玉県民で良かった。
その辺の草でも食べて幸せに暮らします。
最後、何言ってるか分からないけど、まあ、色々考えました、という話。
「お出かけの記録」
- 【番外編】空港が好き
- 20240611 埼玉 東松山市 埼玉ピースミュージアム
- 20240419 東京 三鷹 ぎゃらりー由芽 含真治展
- 20240414 埼玉 入間市 谷田の泉周辺散歩
- 20240408 埼玉 入間市 入間川周辺散歩(花見編)
- 20240104 埼玉 秩父神社
- 20231207 埼玉 飯能市立博物館
- 20231207 埼玉 飯能市 能仁寺
- 20231203 埼玉 深谷シネマ
- 20231117 東京 日本武道館 自衛隊音楽まつり
- 20231030 埼玉 ユナイテッド・シネマ ウニクス秩父
- 20231014 埼玉 入間川河川敷散歩
- 20230914 東京 奥多摩 澤乃井園
- 20230902 東京 上野周辺散策
- 20230729 埼玉 本庄市 埼玉さざえ堂
- 20230728 埼玉 ときがわ町 雀川砂防ダム公園
- 20230709 埼玉 所沢ミューズ 東京ムジーク・フロー演奏会
- 20230624 埼玉 飯能市立博物館~観音寺周辺
- 20230612 埼玉 川越市 ユナイテッド・シネマ ウニクス南古谷
- 20230427 埼玉 入間市 さいたま緑の森博物館
- 20230128 東京 福生 アルルカン 樋詰司展
- 20230119 埼玉 毛呂山町 新しき村
- 20230105 埼玉 秩父神社
- 20220602 埼玉 狭山市 智光山公園 都市緑化植物園
- 20220602 埼玉 狭山市 智光山公園 こども動物園
- 20220330 東京 中野サンプラザ周辺
- 20220201 埼玉 飯能市 宮沢湖 メッツァビレッジ
- 20211015 埼玉 入間市 入間川周辺散歩(廃車編)
- 20211006 三重 伊勢市 おかげ横丁
- 20211006 三重 伊勢市 伊勢神宮 内宮
- 20211006 三重 伊勢市 伊勢神宮 外宮
- 20210319 東京 新宿区 筑土八幡神社
- 20200728 東京 檜原村 払沢の滝
- 20200721 東京 新宿区 新宿K’s Cinema
- 20200528 埼玉 日高市 高麗神社
- 20191107 埼玉 行田市 忍城
- 20191020 群馬 沼田市 沼田城
- 20191019 群馬 吾妻郡東吾妻町 岩櫃城
- 20190928 栃木 宇都宮市 宇都宮城
- 20190922 長野 長野市 松代城
- 20190507 東京 青梅市 七国山薬王寺
- 20190326 東京 新宿区 新宿ピカデリー他
- 20181101 埼玉 川越市 ユナイテッド・シネマ ウニクス南古谷
- 20180822 埼玉 朝霞市 りっくんランド
- 20180720 山梨 冨士御室浅間神社
- 20180816 千葉 成田国際空港
- 20161210 群馬 高崎市榛名山町 榛名神社
- 20160911 埼玉 秩父郡長瀞町 寳登山神社
- 20160709 東京 府中市 大國魂神社
- 20160709 東京 国立市 谷保天満宮
- 20160617 東京 大田区 羽田空港第1ターミナル
- 20151203 埼玉 秩父市 秩父夜祭
- 20151127 東京 千代田区 国立公文書館
- 20140530 東京 神楽坂 赤城神社
- 20140201 東京 東京駅 南北ドームのレリーフ